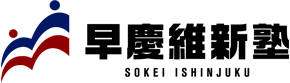慶應・早稲田中学受験 宿題さえやっていれば安心ですか?
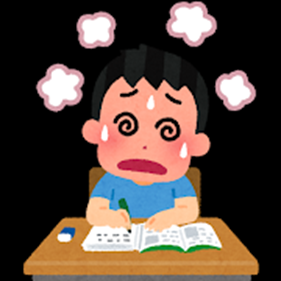
早慶合格への道先案内人、
早慶維新塾 塾長 野田英夫です。
「塾の宿題やっていますか?」
「はい、やっているようです。」
だいたいお母さんはこのように答えます。
でも、実際に私がみてみると、
やってないのがほとんどなんですよ。
「えっ!でも、塾の先生からは宿題やっていると!」
きっと、そうでしょうね。
でも、やってないですね。
理由はこのあと書きますね。
著書「御三家はわかりませんが早慶なら必ず合格させます」が好評発売中です。
すごい勢いで売れています。
まだ読んでいない方は、書店にお急ぎください。
大手塾から毎週、多くの宿題が課せられます。
多過ぎるくらい・・・。
やり切れないくらい・・・。
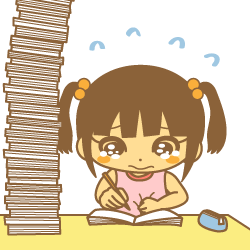
小5にもなると、
宿題をこなすのに深夜12時過ぎまでやっている家庭もあります。
週末にテストがあるときは、
さらに遅くなり・・・。
深夜12時・・・12時半・・・1時・・・
それでもなんとか宿題をこなす。
やらないとお母さんに怒られるし、
それにやらないとテストで取れないから・・・。
でも、そのテストで取れても、
テストが終わった後は、だいたい忘れていませんか?
中学・高校などの定期試験のような勉強では、
意味ないんですよ。
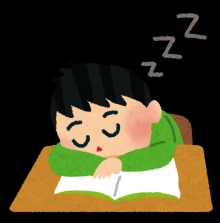
■それで身についているのでしょうか?
カウンセリング時に、
子どものノートをみるようにしています。
それで宿題ノートをみると、
「一応、宿題はこなしている」
でも、これではやっているうちに入らない。
宿題を終わらせてはいます。
でも、終わらせているだけ、
まったく身についていない状態。
いわゆる「作業」なのです。
宿題を終わらせているだけで身についていない。
「作業」を終わらせただけの宿題。
宿題を終わらせることが目的になっている。
■それでも多くの宿題を求めていませんか?
他塾の先生に聞いたことがあります。
「どうしてこんなにたくさんの宿題を出しているの?」
その先生はこのように回答しました。
「多過ぎるくらい宿題を出さないと、保護者からクレームが入りますから」

宿題を少なくすると、
ご家庭からもっと出してくれと言われるそうです。
実際、私の塾でも・・・。
「前の塾ではもっとたくさん宿題が出ていましたよ!」と、
言われることがあります。
でも、そのお子さんの宿題をみると、
やっぱり作業なんですよね。
■ズルさを覚えてしまう弊害も・・・
大手塾からウチの塾に転塾してきた子たちに、
「宿題やってきた?」と聞いてみると、
彼らは自信満々に、
「やってきました!」といいます。
でも、やってきた内容を質問しても、
答えらない・・・。
まったく身についていません。
例えば、漢字練習を宿題にしたときも、
一応、テストでは書けるようにしてあります。
でも、その熟語の意味はまったくわかりません。
もちろん漢字一字の意味もわかりません。
つまり、その子は、テスト用に書けるように練習してきたのです。
書ければいい、ただそれだけ。
「作業」です。
それでは「勉強」になっていない。
言い方は悪いですが、
漢字ではなく「記号」を覚えてきたという感じ。
さらに、そういうことが続くと、
子どもたちは「ズルさ」を覚えるようになります。

「これだけやっておけば先生には叱られないだろう」
「これだけやっておけばお母さんには怒られないだろう」
いい加減で、
中途半端で、
身につかない作業を繰り返すようになります。
それも悪意はなく、無意識にやるようになります。
「宿題やってきましたか?」と聞くと、
「はい、ちゃんとやってあります」と答えますからね。
無意識に「ズルさ」を覚えてしまうんですね。
■何を目的として宿題をしているかを理解させる
子どもたちは何のために宿題しているのでしょうか?
叱られないためですか?
いや、「成績を上げるため」ですよね?
さらに、「志望校に合格するため」ですね。
けっして「叱られないため」ではありません。
「成績を伸ばし志望校に合格するために宿題をやる」
だから身につける勉強をしないといけないわけです。
ここを理解しておかないと本末転倒です。
■たくさんの宿題で安心するのは誰ですか?
当然ながら、一定の「量」は必要です。
一定量をこなさなければ学力がつかないものですから。
しかし、量だけを追って、
身につかない学習をしていても意味はありません。
たくさんの宿題で安心しているのは誰ですか?
たくさん宿題が出て、それを一生懸命勉強している姿をみて、
安心していてはいけませんね。
安心していいのは、
子どもがその内容を「定着できているかどうか」です。
「身に着けているかどうか」です。
身に着ける学習、
身に着けるように宿題もしてください。
「作業」ではなく、「勉強」にする。
「量」よりも、「質」を高めた学習を心がけるのです。
では、また!
もし、受験のことでお困りのことがありましたら、
野田英夫がカウンセリング(無料)を実施します。
お気軽にご連絡ください。